
「肥満」とは、脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態で、体格指数 (Body Mass Index: BMI) 25以上のもの (35以上は「高度肥満」) と定義されています。
肥満症とは、医学的に減量が必要な肥満のことで、ひとつの疾患として扱われます。 ここから、身長と体重を入れるだけで、肥満症チェックができます。ここでは、肥満とその原因を解明する最新科学や情報をご紹介します。

長期間にわたってストレスを感じると、食欲が変化することがあります。そして肥満になるリスクが高まります。ストレスを管理する方法を学ぶことも、体重管理に役立つひとつの方法です。

血液中には、食欲を抑制する化学伝達物質が流れています。この化学伝達物質がどのように作用するのかを理解すれば、体重の調節における生体機能の役割が明らかになり、なぜ肥満を適切に治療するために根底にある生体プロセスに働きかける必要があるかの説明がつくのです。

減量するためには、食べる量を減らし、運動を増やすことが必要です。しかし、私たちの食事の選択や身体活動に関わる多くの側面は、意思の力を超えた複雑な生物学的システムによって決定づけられています。

私たちが暮らす世界と私たちが食べる物は、時代とともに劇的に変化しました。しかし、私たちは生物学的には昔からほとんど変わっていません。このため、私たちの体は飢えを恐れ、エネルギーや塩分、脂質、糖分の豊富な食べ物を探し求めてしまうのです。

肥満や肥満症にはさまざまな要因が関係しているため、減量の達成や維持はたやすいことではありません。実際には、肥満または肥満症の人はどのように自身の体重と向き合っているのでしょうか? 全国47都道府県における調査から、肥満または肥満症の人の減量経験や、減量にまつわる悩みを見てみましょう。

肥満には複数の要因が関与します。しかし一方で、肥満を生活習慣と過剰に結びつけ、「肥満の人は自己管理能力が低い」とする偏見も存在します。こうした偏見は、スティグマと呼ばれ、肥満を抱える人にさまざまな影響を及ぼします。今回は、全国で行われた調査をもとに、肥満や肥満症への認識や、スティグマの実態に迫ります。
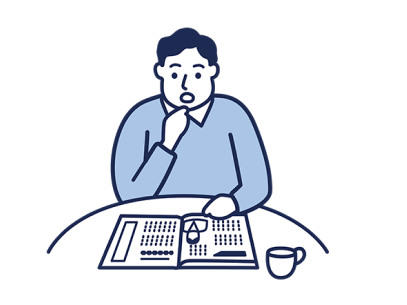
「肥満症」は、肥満があり、肥満に起因ないし関連する健康障害を合併するか、その合併が予測され、医学的に減量を必要とする病態です1。日本における肥満の人の割合は年々増加傾向にありますが、実際に、「肥満症」という疾患はどのくらい認知されているのでしょうか?全国47都道府県における調査から、肥満症の認知率や、肥満症についての相談、診断状況などを見てみましょう。
PromoMats ID: JP23CO00069
The site you are entering is not the property of, nor managed by, Novo Nordisk. Novo Nordisk assumes no responsibility for the content of sites not managed by Novo Nordisk. Furthermore, Novo Nordisk is not responsible for, nor does it have control over, the privacy policies of these sites.